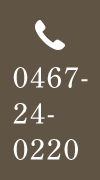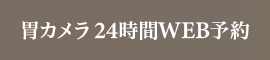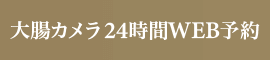下痢
 下痢は冷えや食べすぎなど日常的な原因でも起こる症状です。脱水を起こさないよう水分をしっかり摂取して、1食抜いて胃腸を休め、安静に過ごすことで回復することが多いのですが、それでも下痢が続く場合には疾患が関与している可能性がありますので、早めに受診してください。また、改善しても下痢を繰り返す場合も疾患が疑われます。 特にできるだけ早い受診が必要なのは、嘔吐、発熱、激しい腹痛をともなう場合です。嘔吐で水分を十分にとれない場合は脱水が急激に進むことがありますので、速やかに医療機関を受診してください。 また、便に血や粘液が混じる場合や、同じ食事をした方にも下痢の症状がある場合には、すぐに受診してください。
下痢は冷えや食べすぎなど日常的な原因でも起こる症状です。脱水を起こさないよう水分をしっかり摂取して、1食抜いて胃腸を休め、安静に過ごすことで回復することが多いのですが、それでも下痢が続く場合には疾患が関与している可能性がありますので、早めに受診してください。また、改善しても下痢を繰り返す場合も疾患が疑われます。 特にできるだけ早い受診が必要なのは、嘔吐、発熱、激しい腹痛をともなう場合です。嘔吐で水分を十分にとれない場合は脱水が急激に進むことがありますので、速やかに医療機関を受診してください。 また、便に血や粘液が混じる場合や、同じ食事をした方にも下痢の症状がある場合には、すぐに受診してください。
下痢とは
1日の便の水分量が200ml以上、または1日の便の重さが200g以上と定義されています。実際には計測するのが難しいため現実的な目安としては、形をほとんど保てない場合は下痢と考えてください。 食事などで消化管に入った飲食物は、8時間くらいかけて大腸に運ばれて水分が吸収され、直腸に降りてきて便意を起こし、トイレで排出されます。上行結腸から下行結腸、S状結腸と大腸を進む間に水分が吸収されて適度な固さになりますが、水分を吸収する働きに問題が生じると水分の多い便が出てしまい、下痢となります。なお、身体にとって有害なものを吸収せずに素早く排出させるために下痢が起こっていることもあります。 下痢は、生じるメカニズムによっていくつかのタイプに分けられます。
浸透圧性下痢
水分を保持する浸透圧が高いものを食べすぎると、腸壁から水分が移行して腸管内の水分量が増加し、便がゆるくなります。人工甘味料などの高浸透圧物質の過剰摂取や、乳糖(にゅうとう)不耐性の方が牛乳を飲むとこのタイプの下痢を起こします。
分泌性下痢
分泌液の増加によって便がゆるくなるタイプです。ホルモンバランスが変化して起こる生理中の下痢などがあります。
蠕動運動性下痢
消化管は蠕動運動によって内容物を先に送っています。蠕動運動が亢進すると便が腸管を通過する時間が短くなってしまい、十分な水分を吸収できずに下痢になります。過敏性腸症候群、甲状腺機能亢進症などの疾患の症状として起こる下痢がこのタイプです。また、蠕動運動が低下して増殖した細菌の刺激が下痢を起こすこともあります。
滲出性下痢
腸に炎症が起きると、水分の吸収能力が低下し、粘液の産生亢進や腸管内への滲出液増加が起こって下痢になります。潰瘍性大腸炎やクローン病、虚血性腸炎、ウイルス性腸炎、細菌による腸炎などが疑われます。
下痢症状を伴う消化器疾患
下痢という症状を起こす消化器疾患はかなり多くなっています。急に激しい下痢が起こった場合はウイルス感染による腸炎などが疑われます。下痢を繰り返す場合は、クローン病や潰瘍性大腸炎など難病指定された疾患の可能性もあります。また便秘と下痢を繰り返す症状は、進行した大腸がんで生じていることもあります。大腸がんが大きくなって便の通過が妨げられると、便秘と下痢を繰り返しやすくなります。 激しい下痢がある、慢性的に下痢が続く、便秘と下痢を繰り返す場合には、早めに消化器内科を受診してください。
下痢の検査・治療
検査
 問診で症状の内容、起こり始めた時期や症状の変化、症状を起こすきっかけや直前の食事、既往症や家族歴、服用している薬についてくわしくうかがいます。感染が疑われる場合には、血液検査、便の培養検査を行います。慢性の大腸疾患が疑われる場合には大腸カメラ検査を行います。大腸カメラ検査では大腸全域の粘膜を詳細に調べることができますので、大腸がんや前がん病変の大腸ポリープ、クローン病や潰瘍性大腸炎など、疾患特有の病変の有無を確認できます。また組織を採取できますので、確定診断が可能です。 問診の内容や検査結果を総合的に判断して診断し、適切な治療計画を患者様と相談しながら立てていきます。 病変がなく、慢性的な下痢がある場合には過敏性腸症候群が疑われますので、判断基準にそって診断します。
問診で症状の内容、起こり始めた時期や症状の変化、症状を起こすきっかけや直前の食事、既往症や家族歴、服用している薬についてくわしくうかがいます。感染が疑われる場合には、血液検査、便の培養検査を行います。慢性の大腸疾患が疑われる場合には大腸カメラ検査を行います。大腸カメラ検査では大腸全域の粘膜を詳細に調べることができますので、大腸がんや前がん病変の大腸ポリープ、クローン病や潰瘍性大腸炎など、疾患特有の病変の有無を確認できます。また組織を採取できますので、確定診断が可能です。 問診の内容や検査結果を総合的に判断して診断し、適切な治療計画を患者様と相談しながら立てていきます。 病変がなく、慢性的な下痢がある場合には過敏性腸症候群が疑われますので、判断基準にそって診断します。
治療
下痢の治療では、症状を緩和する薬を処方し、経過を観察します。水分をしっかりとって、消化器への負担が少ない食事や安静を心がけてください。処方される薬は、腸の蠕動運動を抑える薬、腸への刺激を抑える薬、便の中の水分を吸い取って便を固める薬、ビフィズス菌などの整腸薬などがあります。 なお、ウイルス性の胃腸炎などによる下痢に場合には、増殖したウイルスや産生される毒素を排出させるために下痢止めの処方を行わないことがあります。その場合には、脱水を防ぐための水分補給が重要になります。嘔吐もともなって水分補給が十分にできない場合は点滴などで補う必要があります。
下痢が続くときは早めの受診をおすすめします
下痢の症状が強いと脱水を起こす可能性がありますし、慢性的な下痢があると外出がストレスになることがあります。日常的な症状ですから我慢してしまう方も少なくないのですが、適切な治療を行うことで緩和できますし、コントロールできるようになれば日常生活も不安なく過ごせます。疾患が隠れている場合もありますので、下痢の症状をつらいと感じたら気軽にいらしてください。